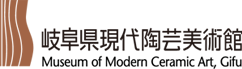「フィンランド・グラスアート 輝きと彩りのモダンデザイン」講演会「フィンランド・グラスアートの魅力」
*終了しました
2024年1月13日(土)14:00-15:30

日時:2024年1月13日(土)14:00〜15:30
講師:土田ルリ子氏(富山市ガラス美術館館長、展覧会監修者)
会場:セラミックパークMINO イベントホール
岐阜県現代陶芸美術館 プロジェクトルームに変更になりました
聴講無料、要事前申込(フォーム)
要事前申込(フォーム) [ 受付開始:12月16日(土)10:00〜 ]
フォームはこちら
*終了しました
2023年7月30日(日)11:00-12:30
多様化する現代社会の教育の場で、ARTとしてのやきものの役割とは…
陶芸家で「大地のこどもたち2023展」審査委員長の伊村俊見氏が、展覧会審査や関連ワークショップの経験をふまえ、教育におけるARTおよびやきものの可能性について考えます。

日時:2023年7月30日(日)11:00-12:30
講師:伊村俊見氏(陶芸家、大地のこどもたち2023審査委員長)
会場:現代陶芸美術館 プロジェクトルーム
参加無料、要事前申込(フォーム)
*終了しました
2023年4月22日(土)14:00〜15:30
講演では、ハンガリーの歴史的・文化的な出来事や、現在の芸術・陶芸の動向全般を振り返りながら、ハンガリー現代陶芸シーンの最重要作家、グループ、期間について、展覧会の構成にそって紹介いただきます。ハンガリー現代陶芸の活発で豊穣な「今」について、ハンガリーから来日する専門家から直接お話を伺える機会です。
日時:2023年4月22日(土)14:00〜15:30
講師:ノヴァーク・ピロシュカ氏(ブダペスト国立工芸美術館 陶磁器・ガラス部門 シニア・キュレーター)
会場:岐阜県現代陶芸美術館 プロジェクトルーム
*聴講無料、日本語通訳あり
要事前申込(電話・フォーム)

やきものにうたう:ハンガリー現代陶芸
独自の陶芸文化で知られるハンガリー。しかしながら、日本ではこれまで、まとまった形でハンガリーの現代陶芸が紹介される機会はありませんでした。本展では、ブダペスト国立工芸美術館による学術協力のもと、110件を超える多彩な作品を紹介します。巨匠から新進気鋭の作家まで、ハンガリーの現代陶芸家たちの多彩な「こえ」が聞こえる作品をご覧ください。
2021年10月3日(日)に開催した青木由香氏によるライブ配信の一部をYoutubeに公開しました。
視聴はこちらから:清流の国ぎふ 自宅で楽しむ文化芸術
台湾・新北市に位置する鶯歌は、台湾有数の陶磁器産地。独自の文化をはぐくんできたその風土や、 台湾の手仕事文化の魅力について、鶯歌からの生中継でお話しいただきます。

青木由香
神奈川県 真鶴生まれ。多摩美術大学卒業後、世界各国を旅行し、2003年から3年間台北で写真、墨絵等を制作するかたわら、日本のメディアにコラムを連載。
2005年12月に台湾の出版社から「奇怪ね〜台湾」を出版。ベストセラーとなり、台湾で一躍話題の人となる。2008年にはビデオブログ「台湾一人観光局」 が、台湾でテレビ化され、2009年に台湾のテレビ大賞に外国人として初めて最優秀総合司会者部門にノミネートされる。
現在は台湾と日本を行き来しつつ、各メディアで大好きな台湾を日本に紹介している。2011年4月〜2019年3月まで、Japan FM Networkにて楽楽台湾のパーソナリティーを務め、2013年には、台湾観光貢献賞を受賞しました。日本での著書は『台湾ニイハオノート』『好好台湾』『最好的台灣』を出版。講談社から2015年『台湾のきほん』2017年『台湾の「いいもの」を持ち帰る』を出版。糸井重里が主宰し、株式会社ほぼ日によって運営されているウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』にて『台湾のまど』を担当。台湾のおもしろさ、おいしさ、たのしさを日本に向けて発信している。2014年に第1子を出産し、子育てをしながら台湾を拠点に活動している。
2021年10月9日(土)よりYouTubeチャンネルにて配信中
台湾現代陶芸の流れとその多彩な独自性についてお話しいただきました。講演のもようは期間限定で配信しています。(日本語翻訳有)
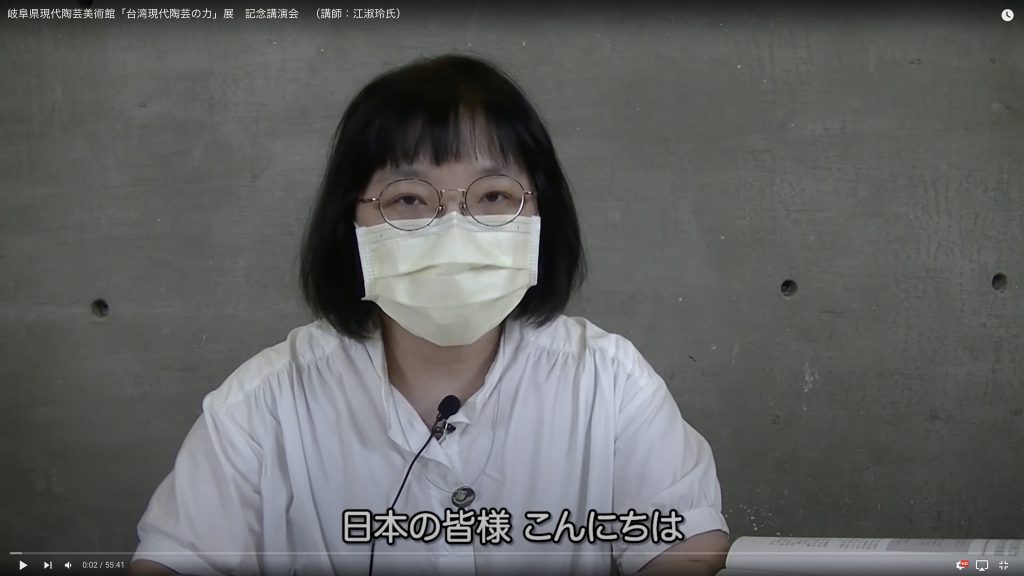
講師:江淑玲氏(新北市立鶯歌陶瓷博物館学芸員)
配信:YouTubeチャンネル
*視聴無料、視聴はこちらから
YouTubeチャンネル「清流の国ぎふ 自宅で楽しむ文化芸術」
*10月9日(土)から10月17日(日)までの期間、講演に関する質問を皆さまから受け付けます。江淑玲氏の質問に対する回答は後日ホームページにて公開いたします。
*終了しました 現在アーカイブ配信中
視聴はこちらから:清流の国ぎふ 自宅で楽しむ文化芸術
2021年10月3日(日) 14:00−15:30 YouTubeにてライブ配信
台湾・新北市に位置する鶯歌は、台湾有数の陶磁器産地。独自の文化をはぐくんできたその風土や、 台湾の手仕事文化の魅力について、鶯歌からの生中継でお話しいただきます。

講師:青木由香氏(エッセイスト)
配信:YouTubeライブ配信
*視聴無料、事前申込不要
視聴はこちらから:YouTubeライブ配信「清流の国ぎふ 自宅で楽しむ文化芸術」
*配信中はYouTubeチャット機能にて質問等を受け付けます。
*講演の一部は、後日アーカイブ配信を予定しております。
青木由香
神奈川県 真鶴生まれ。多摩美術大学卒業後、世界各国を旅行し、2003年から3年間台北で写真、墨絵等を制作するかたわら、日本のメディアにコラムを連載。
2005年12月に台湾の出版社から「奇怪ね〜台湾」を出版。ベストセラーとなり、台湾で一躍話題の人となる。2008年にはビデオブログ「台湾一人観光局」 が、台湾でテレビ化され、2009年に台湾のテレビ大賞に外国人として初めて最優秀総合司会者部門にノミネートされる。
現在は台湾と日本を行き来しつつ、各メディアで大好きな台湾を日本に紹介している。2011年4月〜2019年3月まで、Japan FM Networkにて楽楽台湾のパーソナリティーを務め、2013年には、台湾観光貢献賞を受賞しました。日本での著書は『台湾ニイハオノート』『好好台湾』『最好的台灣』を出版。講談社から2015年『台湾のきほん』2017年『台湾の「いいもの」を持ち帰る』を出版。糸井重里が主宰し、株式会社ほぼ日によって運営されているウェブサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』にて『台湾のまど』を担当。台湾のおもしろさ、おいしさ、たのしさを日本に向けて発信している。2014年に第1子を出産し、子育てをしながら台湾を拠点に活動している。
*終了しました
2021年 7月31日(土) 14:00−15:30
色のついた分厚い吹きガラスの作品を世に送り出した岩田藤七・久利・糸子。3人の作家の日本のガラス工芸史における位置付け等についてお話しいただきます。

講師:齊藤晴子氏(町田市立博物館学芸員)
会場:セラミックパークMINO イベントホール
定員:40名
*聴講無料、要事前申込(電話・メール) [受付開始:6月19日(土)10:00~]
電話 0572-28-3100/メール momca-event@cpm-gifu.jp
*以下の項目をメールにてお知らせください
①件名に「イベント名」
②参加者名(複数名可)
③代表者の氏名、電話番号、住所(市町村まで)
*終了しました
配信期間:2021年 6月2日〜6月30日
2021年5月22日(土)に開催を予定していた「Human and Animal 土に吹き込まれた命」展関連講演会「世界の野生動物を追って」(講師:前川貴行氏(動物写真家))について、YouTubeチャンネル「清流の国ぎふ 自宅で楽しむ文化芸術」にて講演のもようを期間限定で配信いたします。
世界各地を訪れ、野生動物の姿を撮り続ける前川さんが、間近で感じた生き物たちの魅力。
臨場感あふれるお話と、生き物たちの息遣いを感じられる写真をお楽しみください

視聴はこちらから:YouTubeチャンネル「清流の国ぎふ 自宅で楽しむ文化芸術」
*本講演会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実地での開催を中止したものです。
*終了しました
新館長就任記念講演会
「現在形の陶芸」
石﨑泰之氏 (岐阜県現代陶芸美術館新館長、前・山口県立萩美術館・浦上記念館副館長)
岐阜県現代陶芸美術館では、高橋秀治館長退任(令和3年3月31日付け)に伴い、新館長に前・山口県立萩美術館・浦上記念館副館長の石﨑泰之氏が就任いたします(令和3年4月2日付け)。
これを記念し、講演会「現在形の陶芸」を以下の通り開催いたします。
令和3年4月24日(土)14:00‐15:00
| 会 場 | 岐阜県現代陶芸美術館 プロジェクトルーム |
| 定 員 | 30名 |
| ※聴講無料・要事前申込 ※定員に達しました | |
| 受付開始[4月1日(木)10:00~] | |
| 申し込みフォーム https://logoform.jp/f/sgjr9 |

石﨑泰之 (いしざき・やすゆき)
主な活動歴
1960年(昭和35年)愛媛県松山市生まれ。1983年筑波大学芸術専門学群芸術学専攻卒業。1995年山口県教育庁文化課萩美術館・浦上記念館開設準備室、1996年同館専門学芸員、2007年同館学芸課長、2017年同館副館長兼学芸課長、2018年同館副館長。2021年4月から岐阜県現代陶芸美術館館長に就任。
山口県立萩美術館・浦上記念館では、「龍人伝説への道−三輪休雪展」「古萩−江戸の美意識−」「すみすり−赤間硯の造形」「彫金のわざと美 山本晃の詩想と造形」「茶陶の現在−2018萩」など地域の文化資源である工芸とその表現性を紹介する展覧会を企画したほか、「三輪壽雪の世界」「今右衛門の色鍋島」「三輪龍氣生展」といった数多くの陶芸展の巡回展示に携わった。また、わざの美を競うわが国最大級の公募展である日本伝統工芸展の鑑査委員をはじめ、日本陶芸展や女流陶芸展といった現代の先端的な陶芸表現を選抜する全国規模の公募展審査員を務めるなかで、秀でた人材の発掘・育成に関与している。日本の近世陶磁史や陶芸批評に関する著述がある。
主な著作物
『窯別ガイド日本のやきもの 萩』(淡交社 2002年)
『茶陶萩-その伝統と革新性』(萩ものがたり 2014年)
「近世期萩焼茶碗の造形」所収『山口県史 通史編 近世』 (山口県 2022年〔刊行予定〕)
「陶芸新潮流」(毎日新聞西部本社版 2008年1月〜2014年12月連載)